短編アニメーション作品『わからないブタ』、『グレートラビット』がそれぞれ文化庁メディア芸術祭アニメーション部門で優秀賞を受賞するなど、国内外で多くの受賞歴を持つ和田淳さん。今回採択された企画『いきものさん』(仮)は、ゲームエンジン(ゲーム開発環境)「Unity」を使うことによる新たなアニメーション制作方法へ挑戦すると同時に、ゲームアプリへの展開も探る試みです。
和田さんのアドバイザーを担当するのは、編集者/クリエイティブディレクターの伊藤ガビン氏と、マンガ家/神戸芸術工科大学教授のしりあがり寿氏です。
―中間面談は、今回の企画に協力される、プログラマーの薄羽涼彌(うすは・りょうや)さんとプロデューサーの土居伸彰(どい・のぶあき)さん、監修のミヒャエル・フライさんが同席されました。
絵の持ち味を活かせるゲームにするために
和田淳(以下、和田):プログラマーの薄羽さんに協力いただき、過去の作品のパーツや今回の原版を渡して色々試してもらいました。今日はその経過も含めて報告いたします。
―複数の試作を紹介しながら話が進みました。
薄羽涼彌(以下、薄羽):手広く実験してみようということで、和田さんの作画の素材をそのままインタラクションして、いろいろなサンプルをつくってみました。また、2Dの絵を3D上で見るとどう見えてくるか、ということも検討したり、3Dでの新しい和田さんのスタイルというのを模索しました。
土居伸彰(以下、土居):2Dか3Dかについて悩み続けた2ヶ月間でした。さまざまな検討をしていく過程で、Unityのエバンジェリストの池和田有輔さんに会った際、今やっていることを話して一連の作業を見せたところ、「和田さんの作品空間の持ち味は2Dなんじゃないか」という感想をいただきました。和田さん自身もいろいろと試しているなかで、作品が持っている触感が伝わるものが好ましいということでした。それで、和田さんの絵をそのまま活かせる表現は、薄羽さんが最初につくってくれた2Dのもの、という結論に至りました。これらを経て次に今後の方向性を検討しました。
薄羽:ボタン押すとキャラクターが腹筋する仕組みがあるのですが、そのバリエーションをもっと仕込んでいくことを考えています。何をするとどうなるかを、明示的ではなく隠された仕掛けを触りながら発見してくような遊びが良いのではないかと思っています。
土居:和田さんの作品の魅力は、キャラクターたちの関係性や動きのルールがすぐには分からないところだと思うので、それらをゲームのなかでプレーヤーが探っていける仕掛けをつくると、和田さんらしいゲームになるのではないか、とアイデアを練っています。この考え方をベースに、ミヒャエル・フライさんにアドバイスを求めたところ、シリーズなのでいくつかのエピソードをつなぐようなメタレベルでのレイヤーがあった方が良いだろうという意見をいただきました。
和田:1つのストーリーとして、腹筋や腕立て伏せなどの運動を用いたものをつくっていて、こうしたストーリーづくりと、ゲームにしたらどうなるのかを平行して進めているところです。
しりあがり寿(以下、しりあがり):メタレベルの世界をつくるのは大事だと思います。改めて見ると、和田さんの作品はキャラクター単体だけではなくその世界観が魅力ですよね。そういう世界観を設定しないと、そこからゲームが生まれづらいような気がします。
和田:前回は「ミニゲームで終わらないでほしい」と言っていただいて、どう繋げていくかが重要と思っていたのですが、具体的なアイデアがありませんでした。今いただいたアドバイスやミヒャエルさんからの助言を受け、世界観を設定することで上手くできるのかなという感じがします。
伊藤ガビン(以下、伊藤):さまざまなスタディを経て2Dにしたという過程はとても良いと思います。最初の企画を考える段階で、土居さんの思惑としては、短編アニメーションの作家が、作品では食べていけないという問題があったかと思います。それを3Dに引き寄せていくとゲームデザイナーになってしまう。2Dの短編アニメーションの作家が、それにどのように対峙するかという橋渡しの実験としては、正当な方向だという感触を持ちました。
ゲーム性の部分でいうと、小ネタ集にならないためにはメタレベルの世界観と同時に、ゲームデザインとして何か統一できるものがあるとエレガントでしょう。ゲームは基本的に何も考えずに設計していくと、どんどんブラックボックスが増えてしまう。しかし明らかにこれをやったらこうなる、という関係性が最初から見えているほうが、僕は良いと思います。

面白いゲームにする工夫
しりあがり:1つの動作で楽しめるものを何か見つけられるといいですよね。
伊藤:例えば先ほどの腹筋をする動作は、スペースキーを押すことで実行されていますが、「押す」という操作と「起き上がる」というキャラクターの動作が一致していません。『Plug & Play』(ミヒャエル・フライ, 2015)の場合は、インターフェースを上手く触れないということがゲーム性に繋がっていくから気持ちがいい。なかなか合わないという思いが、操作している状況と一致しています。そういうことが発見できると良いと思います。
土居:アウトプットとしてはスマートフォンとPCが基本になると思います。ミヒャエルさんが来年リリースする予定の『KIDS』は、キネクトを利用してインスタレーションでの展開も考えています。Unityの魅力のひとつに、いろいろな形式にアウトプットできるというものがあるので、今回の和田さんの作品も、展開の多様性を視野に入れたいですね。今はシンプルにアニメーションをつくってそれを作品にするスタイルですが、逆にゲームプレイ動画を記録してそれをアニメーション作品としてみせることも可能性としてありえる。そうなってくると、短編アニメーションのつくり方自体も変わってくる。
また、基本的に今までの話は、ゲームのプレーヤーがキャラクターの動作を操る前提ですが、あえてコーチのような立場になる方向も探りたいと思っています。例えば手を叩いたら腹筋してくれるけれど、たまに抵抗されてしまう。そこで、どうしたら腹筋をしてくれるのかを探るのも面白いと思っています。腹筋を重ねると犬がどんどん違うものに変わっていくとか。やり続けると音が変わるなど、変化をつけることでプレーヤーがゲームをし続けるモチベーションになると思います。
伊藤:短編アニメーション作家が食べていけるというのは、具体的にどのぐらい売れることを目標にすると良いでしょうか。例えば、ミヒャエルさんのゲームはどのくらいダウンロードされているんですか。
ミヒャエル・フライ:はっきりとした数字は分かりませんが、『Plug & Play』は20万以上のプレーヤーを得ています。
土居:またミヒャエルさんの場合、新しい作品をつくるときに助成金をもらっています。商業的にも短編アニメーションにもなるということは、どちらの分野の助成金も得られて、新しい作品の制作時間をきちんとつくれる。そういう意味で予算のフレキシブルさみたいなところもありますね。
しりあがり:ミヒャエルさんは成功するまでに、いろいろなトライアンドエラーをしたんでしょうか。
土居:『Plug & Play』が最初のゲーム作品です。優秀なプログラマーとマッチングできたのでよかった。ゲームを制作する人は多くいますが、プログラマーとのマッチングの機会がなかなかなく難しい状況です。そういう意味で、今回のバックアップ体制を活かして、日本での最初の例として実施し、最終的に売れるものになると良いなと思います。
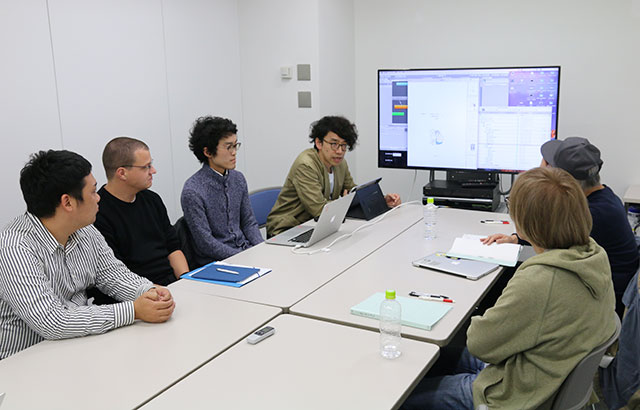
成果発表会に向けて
和田:今後は実際につくる作業に入ります。作画を進め、次回の面談では、映像の部分の完成を目指したいです。
伊藤:何か1つの快感を見つけるまでが大変だと思いますが、そこを妥協せずに進めていってほしいです。一般的なゲームでは、完成したらすぐにリリースされるのですが、任天堂の場合、開発後のチューニングの期間がかなり長い。理想的には、試作、本制作、チューニングで3分の1ずつの時間が使えるといいですね。開発費がかさむのでなかなかできませんが、むしろ個人制作だとそういうことも可能かもしれません。また、ネットの場合はフィードバックを得ながら調整することもできますね。
―次回の最終面談までに、映像の完成を目指しゲームの部分も進めていく予定です。

